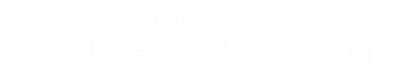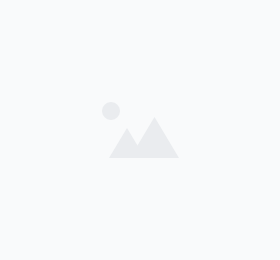【離婚】養育費・婚姻費用について

養育費・婚姻費用の算定方法
基本的には算定表によって算出されますが、標準的なケース(同居していた夫婦が別居し、夫婦の一方が子を監護しており、子が学齢期であれば公立学校に通っている)以外は標準算定方式に立ち返って計算します。
標準算定方式
算定表では解決できない事案においては、算定表のベースとなる標準算定方式に立ち返って計算することが必要になります。
※以下では、「支払い義務者」を夫、「受け取る側・権利者」を妻として説明します。
婚姻費用
①権利者世帯に割り振られる婚姻費用を算出します。
<計算式>
(夫の基礎収入+妻の基礎収入)×(妻世帯の生活費指数)÷(世帯全体の生活費指数)
②夫から妻に支払われる婚姻費用分担額を算出します。
<計算式>
①-妻の基礎収入
夫の基礎収入=X 妻の基礎収入=Y
(X+Y)×妻世帯の生活費指数/世帯全体の生活費指数-妻の基礎収入
養育費
①子の生活費を算出します。
<計算式>
夫の基礎収入×子の生活費指数÷(夫の生活費指数+子の生活費指数)
②夫の養育費分担額を算出します。
<計算式>
①×夫の基礎収入÷(夫の基礎収入+妻の基礎収入)
X×子の生活費指数/夫の生活費指数+子の生活費指数×X/X+Y
用語説明
総収入とは
婚姻費用・養育費の算定において、最初に「総収入」を認定します。
ア 給与所得者
「源泉徴収票」の「支払金額」が総収入です。
イ 自営業者
「確定申告書」から総収入を計算しますが、2パターンあります。
その前に用語の説明をしましょう。
・「課税される所得金額」
=「所得金額」-「所得から差し引かれる金額」
・「所得金額」
=売上金額-売上原価-経費-引当金・準備金等
・「所得から差し引かれる金額」
=税法上考慮される各種の費目を控除したもの。実際には支出されていない控除費目もあるため、婚姻費用・養育費算定の際には「加算される費目」がある。
「加算される費目」
①現実に支出されていないもの
「雑損控除」「寡婦・寡夫控除」「勤労学生、障碍者控除」「配偶者(特別)控除」「扶養控除」「基礎控除」「青色申告特別控除額」「専従者給与(控除)額の合計額(現実の支払いがない場合)」
②算定表で標準額が既に考慮されているもの
「医療費控除」「生命保険料控除」「地震保険料控除」
③現実の支出があっても婚姻費用・養育費の支出に優先しないとされるもの
「小規模企業共済等掛金控除」「寄付金控除」
そして、以下計算式です。
Aパターン:「課税される所得金額」+(①+②+③)
Bパターン:「所得金額」-社会保険料+(専従者給与(控除)額の合計額+青色申告特別控除額)
基礎収入
総収入から税金・社会保険料等の必ず支出する費用を控除し、純粋に生活に充てられる分の収入
必ず支出する費用は、公租公課(所得税・住民税・社会保険料)、職業費(被服費・交通通信費・書籍費・交際費等)、特別経費(住居関係費・保険医療費等)。
基礎収入割合
ア 給与所得者
| 給与収入(万円) | % |
|---|---|
| ~100 | 42 |
| ~125 | 41 |
| ~150 | 40 |
| ~250 | 39 |
| ~500 | 38 |
| ~700 | 37 |
| ~850 | 36 |
| ~1350 | 35 |
| ~2000 | 34 |
イ 自営業者
| 事業収入(万円) | 項目名2 |
|---|---|
| ~421 | 52 |
| ~526 | 51 |
| ~870 | 50 |
| ~975 | 49 |
| ~1144 | 48 |
| ~1409 | 47 |
生活費指数
世帯の収入を、世帯を構成するメンバーにどのように割り振るべきかを示す指数です。
生活費指数算定の根拠は生活保護基準と公立中学校及び公立高等学校基準の教育費をもとに算出されています。
親:100
子0~14歳:55
子15~19歳:90
特別の事情がある場合
私立学校等の学費に関し、加算を認める場合の計算方法
・算定表で考慮されている公立学校教育費相当額を控除する方法
算定表では、次の額が、公立学校教育費相当額として考慮されています。
①子0~14歳:年間13万4217円(月額1万1185円)
②子15~19歳:年間33万3844円(月額2万7820円)
そして、現実に支出している学費から、上記①または②を引いた額を、当事者の収入に応じて分担します。
・生活費指数のうち教育費の占める割合を用いる方法
子の生活費指数のうち教育費の占める割合を計算すると、次のとおりです。
①子0~14歳:13/55
②子15~19歳:32/90
そして、算定表により算出された額に、上記①または②を乗じた額を差し引いた額が、加算額の目安となります。
住宅ローンについて
権利者(妻)居住のローンを義務者(夫)が支払っている場合は、ローンの負担を婚姻費用算定において考慮するのが原則です。算定表は、権利者の住居費を考慮されているにもかかわらず、現実には権利者がその支払いを免れ、その分を義務者が負担することになる為、考慮しなければ義務者側の二重負担となるからです。
ア ローン支払額を特別経費として考慮する方法
ローン支払額から、算定表において考慮済みの標準的な住居費を差し引いた額を上限として、特別経費として考慮します。算定表で考慮済みの住居費とは、算定表の掲載された判例タイムズ1111号294頁「資料2 平成10~14年 特別経費実収入比の平均値」記載の「住居関係費」です。このとき、当事者の収入に応じて該当する欄を、「年間収入階級」ではなく「実収入」でみます。
①年収から考慮すべきローン支払額を控除した額を総収入とみなす方法
②総収入に基礎収入割合を乗じて得られた額から考慮するローン支払額を控除した額を 基礎収入とみなす方法
③考慮するローン支払額を特別経費に加算して基礎収入割合を定める方法
イ 算定表による算定結果から一定額を控除する方法
①権利者世帯の住居関係費相当額を控除する方法
前掲判タ資料2の権利者収入に該当する住居関係費相当額を控除する。
②ローン支払額の一定割合を控除する方法
馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
〒604-0024
京都市中京区下妙覚寺町200衣棚御池ビル2階
TEL:075-254-8277 FAX:075-254-8278
URL:https://www.bababen.work