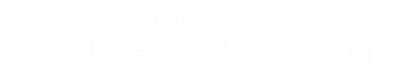役所で知るべきこと
用途地域の種類
①住居系
第1種低層住居専用地域・・・絶対高さ制限、北側斜線制限5m、敷地面積の最低限度
第2種低層住居専用地域・・・絶対高さ制限、北側斜線制限5m、敷地面積の最低限度
第1種中高層住居専用地域・・・北側斜線制限10m
第2種中高層住居専用地域・・・北側斜線制限10m
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
田園住居地域・・・絶対高さ制限、北側斜線制限5m
②商業系
近隣商業地域
商業地域
③工業系
準工業地域
工業地域
工業専用地域
白地地域
都市計画区域、準都市計画区域内で用途地域が指定されていない地域。白地地域の中に特定用途制限地域が定められ、地方公共団体による建築規制がなされる。
防火地域
3階以上(地階含む)又は延床面積100㎡超の建築物・・・耐火建築物が建築可能
上記以外の建築物・・・耐火建築物又は準耐火建築物が建築可能
準防火地域
4階以上(地階除く)又は延床面積1500㎡超の建築物・・・耐火建築物
延床面積500㎡超1500㎡以下の建築物・・・耐火建築物又は準耐火建築物
屋根不燃区域(22条指定区域)・・・屋根、外壁などで延焼のおそれのある部分にコンクリート、瓦、レンガ、鉄鋼など、不燃材を使用することが必要であり、主に防火地域、準防火地域以外の木造住宅密集地に指定
建蔽率
敷地面積に対する建築面積の割合。建築面積とは、建物を真上から見た場合の水平投影面積
容積率
敷地面積に対する延床面積の割合。前面道路幅員が12m未満である場合は、前面道路の幅員に一定率を乗じた数値以下であることが必要となる。
すなわち、
前面道路幅員(4m以上12m未満)×4/10(住居系8地域の場合)・6/10(そのほかの地域の場合)=基準容積率
となる。
建蔽率の緩和措置
①防火地域で耐火建築物の場合―10%増し
②特定行政庁の指定する角地―10%増し
③①及び②の場合―20%増し
容積率の緩和措置
①車庫部分の床面積不算入による緩和
②地階に設ける住宅の容積率緩和
③計画道路および壁面線指定のある場合の容積率緩和
④共同住宅の廊下、階段などの床面積不算入による緩和
都市計画で定める容積率
第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域→50,60,80,100,150,200%のうち都市計画で定める割合
第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域・第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・準工業地域→100,150,200,300,400,500%のうち都市計画で定める割合
工業地域・工業専用地域→100,150,200,300,400%のうち都市計画で定める割合
商業地域→200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1100,1200,1300%のうち都市計画で定める割合
用途地域の指定のない区域(白地地域)→50,80,100,200,300,400%のうち特定行政庁が定める割合
絶対高さ制限
「第一種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」「田園住居地域」。10m又は12m
日影規制
原則高さ10m(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、田園住居地域では、軒の高さが7mを超えるものまたは地階を除く階数が3以上のもの)。冬至の日の午前8時から午後4時までの間、平均地盤面からの高さが1.5mから6.5m(用途地域ごとに指定)の敷地境界線の外側5mから10mの範囲と10mを超える範囲の日影時間をそれぞれ制限する。
注意点
①同一敷地内に建築物が複数ある場合は、ひとつの建築物とみなして適用する。
②日影規制対象外にある建築物でも、高さが10m超で冬至日に対象区域内に日影を生じさせる建築物は、日影規制が適用される。
③建築物が日影規制の異なる区域にまたがる場合は、それぞれの区域に対象建築物があるものとして日影規制が適用される。
道路斜線制限
道路の向かい側境界線から一定距離の勾配面による高さの制限
北側斜線制限
北側前面道路境界線から一定距離の勾配面による高さの制限。「第1種・第2種低層住居専用地域・田園住居地域」の場合高さ5mから、「第1種・第2種中高層住居専用地域」の場合高さ10mから北側境界線上から1mにつき1.25m上がる斜線の内側へ建物を建てる必要がある。
①日影規制が適用される第1種・第2種中高層住居専用地域では、規制の厳しい日影規制が適用され、北側斜線制限の適用はない。
②北側斜線制限の場合、道路斜線制限と違い、建物を後退して建築しても規制が緩和されることはない。
敷地面積の最低限度
大きい敷地を小さく分割する小開発を防止。第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域で適用され、一般的には100㎡の自治体が多い。建築基準法では最低限度は最大でも200㎡。※199㎡の場合、分割して開発不可。
①敷地面積の最低限度に満たない土地にある既存建築物に対しては、適用しない。
②分筆により敷地面積の最低限度に満たない土地となった場合、分筆時期が自治体の制度導入時期より前の場合は建築が認められる場合がある。
都市計画道路
都市計画道路は、一度計画決定されると何年先に事業決定されるかわからない計画に対して地権者は厳しい制限を受け続ける。しかし、長期で事業化の見通しのない都市計画道路を「緩和路線」と指定する自治体も増えている。
既存の道路を拡幅する場合と新たに道路をつくる場合があるが、これは都市計画地図で確認。
建物の新築や増築が許可されるのは計画決定の段階までであり、事業決定段階では、災害時の応急措置による建物など、一部の建築物しか許可されない。また建築が許可される場合でも、「容易に移転、除去できること」を前提とした建築制限が都市計画法53条で規定されている。
①計画決定→計画決定されているが、事業着手の時期等は未定
計画決定期日、計画決定番号、事業決定の予定の有無
②事業決定→計画道路内の土地収用、立ち退き交渉、工事の着工段階
事業の開始時期、完了予定時期
③都市計画道路による建築制限
→原則、ア地階を有しない階数が2以下であること、イ主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造などであること、を満たせば建築許可される
④目的地が都市計画道路と重なる場合
都市計画道路が重なる部分、具体的な建築制限の内容
開発許可
市街化区域および市街化調整区域に関する都市計画が定められた都市計画区域内で、宅地造成など一定規模以上の開発行為を行う場合に、知事または政令指定都市の町の許可を必要とする。開発行為とは、建築物の建築や特定工作物の建設を目的とする土地の区画形質の変更行為のことであり、許可が必要となる開発行為は、市街化区域内では政令で原則1000㎡以上、三大都市圏の一定の地域では500㎡以上とされている。「開発登記簿」「土地利用計画図」「開発許可」「宅地造成許可」「旧住宅地造成事業許可」を確認。
開発許可が不要となる場合
①小規模開発
ア 市街化区域 1000㎡未満の開発行為
イ 非線引き都市計画区域 3000㎡未満の開発行為
ウ 準都市計画区域 3000㎡未満の開発行為
エ 都市計画区域外・準都市計画区域外 1ha未満の開発行為
②公益上必要な建築物
③都市計画事情・土地区画整理事業・市街地開発事業
④市街化調整区域における農林漁業用建築物
建築基準法上の道路・・・4m以上
①42条1項1号(道路法による道路) 国道、都道府県道、市区町村道
②42条1項2号(2号道路) 都市計画事業、土地区画整理事業などによって建造された道路
③42条1項3号(既存道路) 建築基準施行時に既に存在した道路(私道も)
④42条1項4号(計画道路) 都市計画法、土地区画整理法などで2年以内に事業が行われるものとして特定行政庁が指定した道路
馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
〒604-0024
京都市中京区下妙覚寺町200衣棚御池ビル2階
TEL:075-254-8277 FAX:075-254-8278
URL:https://www.bababen.work