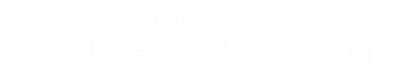社会福祉法人が特別縁故者として認められた裁判例
名古屋高裁金沢支部平成28年11月28日決定は、被相続人が入所していた障害者支援施設を運営する社会福祉法人が特別縁故者として認められた裁判例です。
ところで特別縁故者とは何でしょうか?
特別縁故者について
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とされ、この場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産管理人を選任しなければならないことになり、その旨が遅滞なく公告されます(民法951~953条)。
公告があった後2か月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内(2ヶ月以上)にその請求の申出をすべき旨を公告しなければなりません。
この期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内(6か月以上)にその権利を主張すべき旨を公告することになります。
それでも、この期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができなくなり、相当と認めるときは、家庭裁判所は、特別縁故者の請求によって、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができることとなります(民法958条の3第1項)。
特別縁故者の定義は、「被相続人と生計を同じくしていた者」、「被相続人の療養看護に努めた者」、「その他被相続人と特別の縁故があった者」であり、具体的には内縁の妻(配偶者)や事実上の養子がこれに該当します。
特別縁故者がいない場合、または特別縁故者として認められなかった場合、最終的に相続財産は国庫に帰属することとなります。
名古屋高裁金沢支部平成28年11月28日決定について
この裁判例は、「療養介護は、社会福祉法人として通常期待されるサービスの程度を超え、近親者の行う世話に匹敵すべきもの(あるいはそれ以上のもの)といって差し支えない」場合に、特別縁故者にあたると述べました。
具体的には、
・約35年間にわたって
・知的障害及び身体障害を有し、意思疎通が困難であった被相続人との間において地道に信頼関係を築くことに努めた
・食事、排泄、入浴等の日常的な介助のほか、カラオケ、祭り、買い物等の娯楽に被相続人が参加できるように配慮した
・身体状況が悪化した以降は、昼夜を問わず頻発するてんかんの発作に対応した
・ほぼ寝たきりとなった以降は、被相続人を温泉付きの施設に転居させて、専用のリフトや特別浴槽を購入してまで介助に当たる
・その死亡後は葬儀や永代供養を行うなどした
このように、長年にわたり、被相続人が人間としての尊厳を保ち、なるべく快適な暮らしを送ることのできるように献身的な介護を続けていた場合は、社会福祉法人でも特別縁故者に当たることになるとされました。
馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
〒604-0024
京都市中京区下妙覚寺町200衣棚御池ビル2階
TEL:075-254-8277 FAX:075-254-8278
URL:https://www.bababen.work