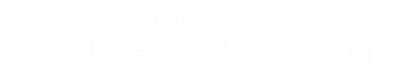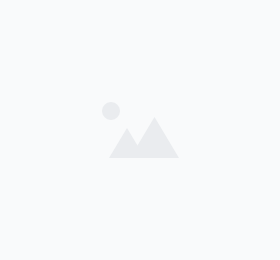相続相談@京都
相続人、相続財産、遺言など、相続にまつわるお悩みはございませんか?
遺産相続は、一生のうちに何度も体験するものではありません。そのため、相続手続きの仕方や、そもそもどのように動けばよいのかわからない方は多いと思います。
相続では、何をいつまでにやるべきでしょうか?その遺産は誰が相続することになるのでしょうか?そもそも他の相続人に被相続人の財産を生前から一人で管理されており隠された遺産があるかもしれないと疑念をもたれているのではないでしょうか?遺産を適切に分けるにはどのような法的手段があるのでしょうか?被相続人が債務だらけで相続放棄をしたいがどうすればよいのか?遺言を発見したがその後どうすればよいのか?
様々な疑問がつきませんが、悩んでいる時間もないのかもしれません。
遺産相続は、紛争防止のために早めに相談に来られてください。
また、相続の難しい点は、ただ財産の問題を取り扱うだけではないところです。ご家族の気持ちの問題を大切にしながら、できる限り、円満な解決を目指していきたいと思います。
- 被相続人の死亡
- 遺言書の確認
- 相続財産調査
- 相続人調査
- 相続人の不存在
- 相続人の範囲をめぐる争い
- 相続の承認・放棄
- 限定承認
- 相続放棄
- 遺産の名義変更等
- 遺産分割
- 投資信託を各相続人で分割する時
- 国債を分割する時
- 遺産である土地を共有するとき
- 一部の遺産について分割方法が決まらない時
- 土地を相続した者が代償金を支払うとき
- 土地を処分しその代金を分割する時
- 遺産が自宅のみで相続人の一人が住み続ける時
- 家族名義の預貯金を遺産と確認した上で分割する時
- 分割協議後に新たな財産が発見された場合にそなえる時
- 遺言と異なる内容の遺産分割を行うとき
- 相続人の一人が行方不明のとき
- 相続人の中に親権者とその子がいる時
- 未成年者に対し親権を行う者がいない時
- 相続人に判断能力がない人がいる時
- 相続人に任意後見契約を締結している人がいるとき
- 相続人中に後見人と被後見人がいる時
- 相続人中に保佐人と被保佐人がいる時
- 相続人の一人が海外在住である時
- 相次いで相続が発生した時
- 相続分を指定する遺言があった時
- 遺産からの家賃収入を分けてもらえない時
- 葬式費用を遺産分割で協議する時
- 調停審判による分割
- 遺産分割後の紛争等
- 特別受益・寄与分・遺留分
- 生命保険金
- 公的年金
- 相続税の申告・納税
- 納税猶予
- その他
被相続人の死亡
在日外国人が亡くなった時
相続にかかる身分関係等について公証役場で宣誓供述書を作成します。相続人全員で遺産分割協議書を作成します。必要な添付書類を添えて法務局に相続登記の申請をします。
相続手続き回避のために遺言代用信託を活用したい
生前に遺言代用信託を設定しておいて委託者の死後は受益者である妻のために受託者が金銭の管理や支払等を行うようにしておきましょう。
親亡き後のために信託を利用して遺産承継をしたい
障害のある子を受益者として遺言で信託を設定し、親が死亡した後の子の生活を支えます。
受益者連続信託を利用して事実上後継ぎ遺贈と同様の効果を持つ資産承継を実現させたい
遺言で後継ぎ遺贈型の受益者連続信託を設定して将来における財産の承継者を定めます。遺言代用信託で後継ぎ遺贈型の受益者連続信託を設定して将来における財産の承継者を定めます。
遺言書の確認
相続に関する事項が記された書置きが見つかった時及び公正証書遺言の探し方
自筆証書遺言はそれがどのような状態にかかわらず直ちに家庭裁判所に提出し検認の手続きを取る必要があります。公正証書遺言の原本は公証役場に保管されているため登録された遺言は検索が可能です。
封印のある自筆証書遺言を開封したい
必要な手続きがあれば教えて下さい自筆証書遺言は勝手に開封せずそのままの状態で直ちに家庭裁判所に対して提出して検認の手続きを取る必要があります。検認された遺言書については裁判所に対して遺言書検認済証明申請をすることになります。
無効と思われる遺言書が見つかった時
遺言書に関してはその内容が偽造であり無効であると思われたとしても、まず家庭裁判所の検認の手続きを取る必要があります。その上で遺言書が無効であることの確認調停を申し立てることとなります。調停が不成立に終わった場合ないし審判がされないことになった場合に無効確認訴訟を起こすためには、調停不成立証明書を取る必要があります。調停で無効の確認が出来なかった場合には地方裁判所に対して遺言無効確認の訴訟を提起します。
在日外国人の遺言書を日本で検認したい
自筆証書遺言の場合には、日本の家庭裁判所に遺言書の検認の申立が可能です。その場合は、父親が死亡したことがわかる住民票を添えて住所地の家庭裁判所に申立をします。検認を終えた後、家庭裁判所に対し検認を受けた旨の証明の申立をします。
相続財産調査
不動産の保有状況を調査する時
不動産の所在が概ねわかっている場合には当該不動産の権利関係を確認するために不動産登記簿閲覧します。次に登記事項証明書を取得します。名寄帳で不動産の所在を調べることもできます。相続税の額を算定するために不動産の評価を調べます。
相続債務の有無を調査する時
金融機関に対して被相続人の借入金の残高等についての問い合わせをします。被相続人が営んでいた事業を廃業する場合には取引業者や金融機関に対して廃業通知を出します。
相続財産の中に賃貸物件があるとき
賃借人に対して賃貸人が変更した旨の通知をします。アパート経営を継続しない場合には賃借人に対して賃貸借契約終了の申し入れをします。相続人全員が相続放棄した場合は相続財産管理人の選任の申立をします。
相続財産の中に賃借物件があるとき
賃貸人に対して賃借人が変更した旨の通知をします。賃貸借契約を継続しない場合には賃貸人に対して賃貸借契約終了の申し出をします。
相続財産の中に係争中の土地がある時
民事訴訟により所有権の帰属を確定させます。本件の場合は他の相続人に対し所有権移転登記手続請求をすることになります。他の相続人に対して遺産分割の協議の申し入れをします。遺産分割の合意が成立しない場合には遺産分割禁止の調停を申し立てることもできます。
土地建物が相続財産かどうか争いがある時
遺産の範囲に争いがある場合は遺産に関する紛争調整調停を申し立てます。調停成立時には遺産であることを確認する調停条項を作成します。調停が成立しなかった場合訴訟を提起します。
相続人調査
相続人の存在が不明であるとき
被相続人の戸籍謄本等を請求し相続人の存否を調査します。相続財産管理人選任の申立てをします。相続人捜索公告の申立をします。相続人が存在しない場合、特別縁故者への分与を請求します。
所在や生死が分からない相続人がいる時
不在者財産管理人選任審判の申立をします。不在者財産管理人の権限外行為許可審判の申立をします。不在者財産管理人が他の共同相続人と遺産分割協議を成立させます。失踪宣告審判の申立をします。失踪宣告の審判が確定した場合には失踪届けをします。
行方不明になっていた相続人が生きていた時
失踪宣告取消の申立をします。失踪宣告取消の審判に基づき失踪宣告取消の届出をします。失踪宣告取消を受けた者は既に行われた遺産分割について財産の返還を請求することができます。
相続人の中に胎児がいる時
子の出生を待って特別代理人選任の審判申立をし遺産分割協議をします。
内縁の子が相続する時
認知の訴えを提起します。認知の届出をします。そして特別代理人選任の審判申立をし、遺産分割協議をします。
財産を相続させたくない相続人がいるとき
相続権を剥奪するためには被相続人が家庭裁判所に推定相続人廃除の審判申立をします。推定相続人廃除の申立後審判が確定する前に、相続が開始した場合、相続財産をめぐる混乱を防止するため家庭裁判所は遺産管理人の選任、その他の遺産の管理に関する処分を命ずることができます。
推定相続人廃除の審判が確定し相続人が自ら財産を管理することができるようになった時、家庭裁判所は申立てにより又は職権で遺産管理人選任処分の取消しの裁判をしなければなりません。推定相続人廃除の審判が確定した時は被廃除者である相続人は直ちに相続権を失います。廃除の届出によって効力が発生するものではありません。申立人は審判確定の日から10日以内にその旨の戸籍の届出をしなければなりません。
遺言により相続人廃除の意思表示があった時
遺言執行者は推定相続人を廃除する遺言の効力を生じた後遅滞なく家庭裁判所に廃除の審判の申立をしなければなりません。審判が確定するまでの相続財産をめぐる混乱を防止するため家庭裁判所は遺産の管理に関する処分を命ずることができます。推定相続人廃除の審判が確定し相続人が自ら財産を管理することができるようになった時、家庭裁判所は申し立てにより遺産管理人選任処分を取り消さなければなりません。推定相続人廃除の審判が確定した時は被廃除者である相続人は直ちに相続権を失います。廃除の届出によって効力が発生するものではありません。遺言執行者は審判が確定した日から10日以内にその旨の戸籍の届出が必要です。
推定相続人の廃除を取り消す時
推定相続人廃除の取消しをするためには被相続人が家庭裁判所に推定相続人廃除の取消しの審判の申立をし、推定相続人廃除の取消しの申立て後審判が確定する前に相続が開始した場合に相続財産をめぐる混乱を防止するため家庭裁判所は遺産の管理に関する処分を命ずることができます。推定相続人廃除の取消しの審判が確定し、相続人自らが財産を管理できるようになった時は、家庭裁判所は申立てにより又は職権で遺産管理人選任処分の取消しの裁判をしなければなりません。推定相続人廃除の取消しの審判が確定したときは申立人はその日から10日以内にその旨の戸籍の届出が必要です。
遺言により推定相続人の廃除を取り消す時
遺言執行者は推定相続人廃除を取り消す遺言が効力を生じた後遅滞なくその推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求しなければなりません。推定相続人廃除の審判が確定するまでの相続財産の混乱を防止するため家庭裁判所は遺産の管理に関する処分を命ずることができます。推定相続人廃除取消しの審判が確定し、相続人が自ら財産を管理できるようになった時は家庭裁判所は申立てにより又は職権で遺産管理人選任処分の取り消しの裁判をしなければなりません。推定相続人取消しの審判が確定した時は遺言執行者は審判が確定した日から10日以内にその旨の戸籍の届出が必要です。
相続人の不存在
相続人のない財産から債務の弁済を受けたい時
相続人のない相続財産から債権を回収するためには、相続財産管理人の選任を申し立てます。相続財産管理人は相続債権者受遺者を確定するため請求申出の催告をします。債権者は相続財産管理人に対して債権届を提出し相続財産から弁済を受けることができます。
相続人のない財産を管理処分してもらいたい時
相続人のない財産を管理処分してもらいたい場合には、相続財産管理人の選任を申し立てます。相続財産管理人は相続財産を管理し、家庭裁判所に管理状況を報告します。相続財産管理人が相続財産を処分する場合には家庭裁判所に権限外行為の許可を申し立てます。
相続人のない財産から葬儀費用等を支払ってもらいたい時
相続人のない財産から葬儀費用等の支払を受けたい場合には、相続財産管理人の選任の申立をします。相続財産管理人がその認定によりあるいは権限外行為許可の審判を申し立てて葬儀費用を支払います。
相続人のない財産を国庫帰属させたい時
相続財産管理人は相続人が不存在であることを確定するため相続人捜索の公告を申し立てます。相続財産管理人は国庫に帰属する財産を確定するため報酬付与の申立をします。相続財産管理人が預金を国庫に帰属させる場合、裁判所債権管理官の指定する口座に納付します。相続財産管理人が不動産を国庫に帰属させる場合、所轄財務局長に引き継ぎます。
相続財産管理人選任後に相続人が現れた時
相続人は相続人の捜索期間内に相続権を申し出ます。相続財産管理人は遅滞なく相続人に対し残存する相続財産を引き継ぎます。相続人又は相続財産管理人は相続財産管理人選任処分取消の審判を申し立てます。相続財産管理人は任務終了にあたり管理終了報告書を家裁に提出します。
特別縁故者の審判に不服があるとき
特別縁故者に対する財産分与の申立てを却下する審判に不服がある場合は即時抗告の申立をします。分与の審判があった時分与の額に不服がある場合は即時抗告の申立ができます。
相続人の範囲をめぐる争い
子の認知を巡って争う時
認知が真実に反し認知者と被認知者の間に血縁関係がない場合には民法786条に基づく認知無効の調停を申し立てます。調停で合意が出来なかった場合、認知無効請求の訴訟を提起します。
内縁の子の認知を巡って争う時
認知を求める相手である父が死亡しているので検察官を被告として認知請求訴訟を提起します。そして亡くなった父との親子関係が認められると亡くなった父の遺産であるマンションを相続することも可能となります。
養子縁組を巡って争う時
養子縁組無効の調停を申し立てます。養子縁組無効の確認請求の裁判を提起します。義理の兄から死後離縁許可の審判を得た上で協議離縁します。
祭祀財産を承継する相続人が明らかでないとき
祭祀財産は被相続人からがその承継者を指定せず慣習が不明であるときは家庭裁判所に際し財産の承継者の指定を求める調停または審判の申立をします。調停が成立した場合は祭祀財産の承継者の指定を記載した調停条項を作成します。
他の相続人により相続分が侵害されている時
相続人全員を相手方にして遺産分割の協議を申し立てることができ、遺産分割の協議が調わないときは家庭裁判所に遺産分割の調停または審判の申立てをすることができます。遺産分割の調停が成立した時は遺産分割の内容を記載した調停条項を作成します。相続財産として争いがあることから遺産分割の協議が出来なかった時は遺産であることの確認や相続登記の抹消登記請求等の民事訴訟を提起することになります。相続登記の更正登記手続請求訴訟を提起した場合、被告が民法884条の消滅時効を援用し更生登記手続きが認められない場合があります。
相続の承認・放棄
限定承認
相続財産の中に一部借金がある時
相続の限定承認申述の申立てを家庭裁判所にします。
限定承認をした後に借金を清算する時
限定承認の広告の手続きをします。知れたる債権者に対しては個別に催告します。滞納税金と相続債権者に対する弁済は原則としている税金が優先します。
限定承認の申述に後見監督人の同意がなかった時
被後見人又は後見人が限定承認の申述をした家庭裁判所に対して書面をもって限定承認の取り消しの申述をします。
限定承認をした条件付き債務の弁済額を確定させたい時
鑑定が必要な条件付き債権又は存続期間の不確定な債権の債権目録を提出する必要があります。また届出債権に対する調査をして最近内容を明確にしておく必要があります。
限定承認した相続財産の価格弁済をする時
限定承認者が相続財産を取得する方法としての競売と競売を差し止める手続き限定承認後に行う相続債務の清算手続きにおいて相続財産を看過する必要がある場合に限定承認者はこれを競売に付さなければなりません。しかし、相続債権者受遺者は相続財産の客観的価値によって弁済を受けるという立場にあるため相続債権者等にとっては適正な価格による弁済を受けられるのであれば当該相続財産を相続人に帰属させることを認めても損害はないので、その相続財産の適正な価格を鑑定する鑑定人の選任を家庭裁判所に申し立てその鑑定価格を相続財産に組み入れて競売を差し止める権利が認められています。
包括遺贈を限定承認する時
叔母の相続人全員と共同して家庭裁判所に対して相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に限定承認の申述を行います。
相続放棄
相続財産のほとんどが借金であるとき
積極財産、消極財産を問わず被相続人の権利義務を一切承継しないようにするためには、相続放棄の申述を家庭裁判所にします。
遺産分割協議の後多額の債務があることが分かった時
家庭裁判所に相続放棄の申述をします。既に成立した遺産分割協議に無効原因がある場合には、遺産分割協議の無効を主張します。
相続人が相続放棄もしないまま死亡した時
被相続人Aの相続について被相続人Bが相続の承認放棄をしないまま死亡した場合に、被相続人の相続人が被相続人の相続についてのみ放棄するには被相続人Aの相続を放棄することを明確にして相続放棄の申述をしなければなりません。
相続放棄がされているか知りたい時
相続人が相続放棄したかどうかを調べるためには、家庭裁判所に相続放棄の申述の有無についての照会をします。相続人が相続放棄したことの証明を得るためには家庭裁判所に相続放棄申述受理証明書を申請します。
被保佐人が単独で相続放棄したとき
相続人が家庭裁判所に受理された相続放棄を取り消すには家庭裁判所に対してその旨の真実をします。
脅迫により行った相続放棄の申述を取り消したい
相続放棄取消申述を家庭裁判所に申し立てで相続放棄の取消しをします。
破産者である相続人が相続放棄を行った時
夫の負債が遺産を上回ることが明らかである場合は破産裁判所の許可を得た上で家庭裁判所に対して相続放棄を承認する旨の真実をします。
遺贈を放棄したい時
家庭裁判所に対して包括遺贈放棄の申述をします。
相続放棄を考慮中の相続人が相続財産を管理できない時
熟慮期間中相続人が病気や遠隔地に居住している等の理由によりあるいは共同相続人間で紛争がある等の理由により相続財産の適切な管理が困難である場合には、家庭裁判所は利害関係人又は検察官の請求により相続財産の保存に必要な処分を命ずることができます。相続財産の保存に必要な処分としては、相続財産管理人を選任することがもっとも一般的であり実効性があります。利害関係人は家庭裁判所に対して相続財産管理人選任の審判を申し立てることができます。なお相続財産管理人選任を含む相続財産の保存に必要な処分に関しては即時抗告は認められません。
放棄をした相続人が財産分与を受けようとするとき
相続放棄をした相続人であっても特別縁故者になりうるとされています。そこで財産分与を受けるためには相続人捜索の公告期間満了後の3か月以内に特別縁故者に対する財産分与審判の申立をします。
遺産の名義変更等
預貯金等
遺産分割前に預金の払い戻し請求を受けるとき
被相続人の預金口座のある金融機関に対し、遺産分割協議前の払い戻しを依頼すること、または、家庭裁判所に審判前の処分保全を申し立てることができます。
相続人が銀行預金の名義変更をするとき
被相続人の預金口座のある金融機関に対し、残高証明書の発行を依頼し、名義変更の届出をします。
相続人が貯金の払い戻しを受けるとき
貯金残高確認の必要があるときは、ゆうちょ銀行または郵便局に対し、貯金残高証明書を請求します。
相続確認表に必要事項を記入して相続届け出をします。
そして、貯金事務センターから送付される相続手続請求書等に払い戻しまたは名義書換請求等を記入して提出します。
不動産
胎児が法定相続人として不動産を相続したとき
夫が二カ月前に死亡し、夫名義のマンションがあるのですが、どうしたらよいでしょうか。現在、私は妊娠六か月で、他に三歳の長男がいます。
胎児は、相続については既に生まれたものとみなされますので、胎児を含めて法定相続分による相続登記を申請することが出来ます。
相続登記の後、胎児が出生した場合、相続登記に出生した子の氏名、住所を記載するために登記名義人氏名・住所変更の登記を申請することになります。
相続登記の後、胎児が死体で生まれた場合には、相続登記の持分を変えるために所有権更正登記を申請することになります。
子が遺産分割による不動産を相続したとき
子と母親とが遺産分割協議をするにあたっては利益相反となるので子について特別代理人選任の申立を行います。
母親と子の特別代理人との間で遺産分割協議をします。
遺産分割協議書に基づき、子を相続人として、相続を原因とする所有権移転登記を申請します。
特別縁故者が不動産を取得したとき
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とされますので、相続財産管理人の選任の申立をします。
相続財産である不動産は相続財産法人に帰属することになりますので、相続財産法人への登記名義人表示変更登記を申請します。
特別縁故者は、家庭裁判所に対し、特別縁故者に対する財産分与の申立をします。
財産分与の審判が確定した後、相続財産法人から特別縁故者への所有権移転登記を申請します。
遺言により不動産を遺贈されたとき
遺言が自筆証書遺言の場合には家庭裁判所に検認手続きをします。公正証書遺言の場合は検認は不要です。遺言書に基づき、遺贈を原因とする所有権移転登記申請をします。遺言執行者がいるときは、受遺者と遺言執行者との共同申請で、遺贈を原因とする所有権移転登記申請をします。
遺産分割調停の結果に従って相続登記をするとき
法定相続の登記がなされていない場合は、相続を原因とする登記申請をします。
法定相続の登記がなされている場合は、遺産分割を原因とする登記申請をします。
他の相続人から相続分を譲渡されたとき
相続分を譲渡し、相続分譲渡証書または相続分譲渡証明書を作成します。他の相続人に対し、相続分譲渡通知書を送付します。相続分の譲渡による所有権持分移転登記を申請します。
相続人不存在の不動産を時効取得したとき
相続人不存在の不動産について時効取得を原因とする登記をするには、まず相続財産管理人の選任を申し立てる。
被相続人から相続財産法人へ所有名義を変更する氏名および住所変更登記を申請します。
相続財産管理人が裁判所から権限外行為の許可を受け、時効取得者を権利者とし相続財産管理人と共同で、時効取得を原因とする所有権移転登記を申請します。
裁判所の許可が受けられなかった場合は、相続財産管理人を被告として訴訟を提起し、判決に基づき、時効取得者が単独で、時効取得を原因とする所有権移転登記を申請します。
死亡した共有者に相続人がいないとき
相続人のない相続財産について利害関係人として、相続財産管理人の選任を申し立てます。相続財産管理人が、被相続人の共有持分について相続財産法人名義への氏名及び住所変更登記を行います。特別縁故者の不存在が確定したときは、共有者を権利者として、特別縁故者不存在確定を原因とする被相続人の持分全部移転登記を申請します。
アパートを相続したとき
土地建物について、遺産分割協議に基づいて、相続を原因とする所有権移転登記申請をします。賃貸人の地位の承継を賃借人に通知します。
死因贈与契約により不動産を取得した時
死因贈与執行者がある場合には死因贈与契約書に基づき寄贈者と死因贈与執行者との共同申請で贈与を原因とする所有権移転登記申請を行います。死因贈与執行者がない場合、死因贈与契約書に基づき受贈者を権利者、共同相続人を義務者として贈与を原因とする所有権移転登記申請を行います。死因贈与契約書で執行者が選任されておらず共同相続人の協力を得られない場合には、家庭裁判所に死因贈与執行者の選任の申立てをすることができます。
農地を相続する時
被相続人名義の農地について相続人間で遺産分割協議を行い相続人の一人が農地を相続することとした場合には相続を原因とする所有権移転登記の登記を申請することになります。この場合農地法所定の許可は不要ですし、登記申請の際にも許可書の提供は必要ありません。既に法定相続分で共同相続した旨の相続登記をした後に遺産分割協議を行い相続人の一人が農地を取得することとした場合には遺産分割を原因とする持分の移転登記をすることになります。この場合でも農地法所定の許可は不要ですし、登記申請の際にも許可書の提供は必要ありません
山林を相続する時
平成23年4月の森林法改正により平成24年4月以降地域森林計画の対象となっている森林の土地の所有者となったものは市町村長への事後届出が必要となりました。所有権取得の原因は限定されていないので、相続により森林の土地の所有権を取得した場合もこの届出を要します。この届出は土地の所有者となった日から90日以内に取得した土地のある市町村長に対して行います。
農地遺贈された時
農地について所有者を移転する場合、原則として農地法所定の許可を得る必要があります。遺贈により所有権を移転する場合、包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈の時には許可は不要ですが、相続人以外の者に対する特定遺贈の時には許可が必要です。以上により農地の名義を変える所有権移転登記の手続きについては、遺贈について遺言執行者が選任されている場合と選任されていない場合とで登記の申請人や必要書類が違ってきます。
相続財産の中に農地がある時
農地を相続する場合、農地法による農業委員会の許可は不要ですが、農業委員会への届出が必要です。相続した農地を売却する場合には農業委員会の許可が必要となります。相続した農地を賃借する場合も農業委員会の許可が必要ですが、その規制は売買よりも緩和されています。
相続した不動産の名義が先代のままである時
まず父の死亡によって開始した相続について遺産分割協議をし、ついで兄の死亡によって開始した相続について遺産分割協議をするのが原則ですが、両者を一緒に行うことも可能です。遺産分割協議書についても一つの遺産分割協議書に第一の相続についての協議事項と第二の相続についての協議事項をまとめて記載することができます。登記についても第一の相続についての相続登記と第二の相続についての相続登記を順次申請するのが原則ですが本事例のような場合には二つの相続についての登記を一件の登記として申請することができます。
不動産の名義を変えられたら
相続回復請求の調停を申し立てるか最初から地方裁判所に訴訟を提起します。調停を申し立てたが不成立となった時は訴訟を提起します。
相続人の中に破産者がいる時
相続開始前に相続人の一人について破産手続き開始決定がなされ、破産管財人が選任されていても、破産者自らが遺産分割協議に参加することができます。相続が開始した後に相続人の一人について破産手続き開始決定がなされ、破産管財人が選任された場合には、遺産分割協議において、破産管財人が破産者に代わって当事者適格を有します。破産管財人は破産裁判所の許可を得て他の相続人全員との間で遺産分割協議を成立させることができます。破産手続き開始前に遺産分割協議がされていた場合その遺産分割協議が否認の対象になることがあります。遺産分割協議に基づいて相続を原因とする所有権移転登記を申請します。
株式等
株式を相続したとき
遺産分割協議が成立するまでの間は、会社等に対し株式の権利行使者及び株主に対する通知催告の事業者の指定通知をします。会社等に対し株主名簿記載事項証明書を請求します。遺産分割協議が成立した後、会社に対し株主名簿の名義書換請求をします。株式名簿管理人が置かれているときは、株主名簿管理人である信託銀行等に対し、名義書換請求します。
上場株式遺贈された時
証券会社信託銀行等に対し、残高証明書を請求します。証券会社に対し、取引口座の移管の手続きをします。株式が信託銀行等の特別口座で管理されている場合には信託銀行等に対し名義変更手続きをします。
相続した株式の株券が見つからない時
会社等に対し株券喪失登録の請求を行います。株券の再発行を受けた後に名義書換請求の手続きをします。
債務
相続財産の中に債務がある時
相続人は、被相続人の債務も一応承継しますが、相続放棄の申述を家庭裁判所にすることにより、すべての債務を承継しないで済みます。同じく家庭裁判所に限定承認の申述をすれば、積極財産の限度においてのみ、被相続人の債務を承継することができます。住宅ローンなどの債務を引き継ぐ場合、金融機関との間で債務引受の契約をすることになりますが、団体信用生命保険に加入している場合は、保険金によりローンが完済されることになります。
相続財産の中に保証債務がある時
連帯保証債務も原則として相続人が承継することになりますがその責任は法定相続人の範囲で承継することになります特定の相続人が連帯保証債務を承継する場合債権者との間で保証書や債務引受契約書といった書類を取り交わすことになりますなお保証債務が女性の場合は当然に相続人に引き継がれるとは限りませんお詳細も一切承継したくない場合は家庭裁判所に対し相続放棄の申述をします詳細を積極財産の範囲内でのみ承継したい場合は限定承認の申述をします。
抵当権付き不動産を相続する時
土地建物について遺言により相続を原因とする所有権移転登記申請をします遺言による債務の承継について抵当権の債務者の変更登記申請をします
抵当権付き不動産を遺贈された時
遺言で執行者が選任されていない場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立をします。以上を原因とする所有権移転登記申請をします。抵当権の債務者について、相続を原因とする変更登記申請をします。抵当権の債務者について債務引受を原因とする変更登記申請をします。
抵当権付き不動産を相続する時
土地建物について、相続を原因とする所有権移転登記申請をします。根抵当権の債務者について法定相続により相続人全員を債務者とする変更登記をします。根抵当権の債務者について指定債務者の合意の登記をします。
その他の権利
貸金債権を相続する
遺贈義務者である相続人、包括受遺者または遺言執行者から、債務者に対し貸金債権譲渡通知書を配達証明付内容証明郵便にて発送の上、債務者に請求します。受遺者が債務者から貸金債権譲渡承諾書を取得し公証役場にて確定日付の付与を受けたうえ、債務者に請求します。
ゴルフ会員権を相続した時
会則により相続が認められていれば、遺産分割後にゴルフクラブ所定の名義変更請求書を提出します。会則により相続が認められていなければ預託金返還請求をすることになります。
自動車を相続した時
運輸支局又は自動車検査登録事務所に移転登録申請書、自動車検査証記入申請書を提出します。都道府県の自動車税事務所に自動車取得税自動車税申告書を提出します。
賃借権を承継する時
土地の賃貸人に対し建物を移動されたので通知し土地賃借権の譲渡承諾を請求します。公正証書遺言により遺言を原因とする建物の所有権移転登記を申請します。遺言執行者がいる場合には遺贈による所有権移転登記は遺言執行者を義務者として申請します。
相続財産の中にゴルフ会員権があるとき
預託金会員制ゴルフクラブの会員契約上の地位は相続することができますが、会員の死亡を理由とする預託金返還請求はできません。退会により預託金返還請求をすることができます。
現物分割をすることが難しい相続財産がある時
遺産分割については遺言による指定がなければ相続人間の協議で決定します。即時の分割が不能の場合、遺産分割禁止を申し立てることができます。分割できない相続財産の場合代償金を支払い所有権を取得することができます。
銀行の貸金庫に相続財産があるとき
貸金庫上の権利義務も相続の対象となり、銀行に相続手続き依頼書を提出します。相続人の一部に借主の地位を承継させる場合、遺産分割行います。解約も原則全員で行います。
相続人名義の預貯金がある時
預金名義人がその預金を相続財産であると認め、相続人全員が承認した場合は、これにつき遺産分割を行うことになります。自己名義の預金についてそれが自分の財産であると認識したとき預金名義人はそのまま預金債権の権利を行使すればよく、これに対し他の相続人が相続財産であると主張する場合には、その相続人が遺産分割の調停申立又は預金債権が被相続人の遺産であることの確認を求める訴訟を提起します。
相続財産の一部を分離してもらいたい時
相続財産と相続人の固有財産が混合されると弁済を受けられない危険がある場合があります。このような場合、相続財産の分離審判申立をすることができます。財産分与審判によって債権の満足を受けることができます。
相続財産の一部を分離し相続人の財産から弁済を受けたい時
被相続人の相続財産がマイナスの場合相続人の固有財産と混合されると相続人の債権者は弁済を受けられない危険性が生じます。相続人の債権者は相続財産の分離審判申立をすることで満足を得ることができます。
遺産分割
投資信託を各相続人で分割する時
相続人全員で遺産分割協議書を作成します。金融機関所定の名義変更の書類に相続人全員で署名押印し、戸籍謄本及び印鑑登録証明書を付けて提出します。相続人全員での話し合いがつかない場合には遺産分割の調停の申立をします。相続人間で協議が成立しない場合に金融機関に対して普通預金と同じように法定相続分を単独で請求できるかについては投資信託の種類が何かによって結果を異にするでしょう。
国債を分割する時
遺産分割後に金融機関に所定の相続手続依頼書を提出します。
遺産である土地を共有するとき
遺産分割についての話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成します。不動産を共有とする協議が成立した場合、共有の相続登記手続きをします。将来共有物を分割する場合は共有物分割の手続きをします。
一部の遺産について分割方法が決まらない時
自宅の土地建物につき遺産分割を成立させ遺産分割協議書を作成します。借地人が後日分割するか決めこれを遺産分割協議書に記載しておきます。
土地を相続した者が代償金を支払うとき
土地を単独に取得する相続人が土地を取得しない相続人に対し債務の負担をする旨の遺産分割協議書を作成します。
土地を処分しその代金を分割する時
換価分割の遺産分割をしその協議書を作成します。
遺産が自宅のみで相続人の一人が住み続ける時
賃貸借、使用貸借等の用益権の設定をする遺産分割もします。
家族名義の預貯金を遺産と確認した上で分割する時
家族名義の預金を相続人の預貯金と確認した上で遺産分割します。
分割協議後に新たな財産が発見された場合にそなえる時
後日遺産の存在が判明した場合の遺産分割の方法について行為をし、その行為内容を遺産分割協議書に明記します。
遺言と異なる内容の遺産分割を行うとき
相続人全員の総意により遺言と異なる内容の遺産分割を行う旨を明らかにした遺産分割協議書を作成します。
相続人の一人が行方不明のとき
相続人の中に行方不明者がいて遺産分割協議ができない場合はまずそのものを不在者として不在者の財産管理人選任審判の申立をします。不在者の財産管理人が相続人等と遺産分割協議をします。財産管理人は遺産分割協議書作成前に権限外行為許可審判を得ている必要があります。財産管理人は家庭裁判所に命じられた場合は財産の状況の報告及び管理の計算をしなければなりません。
相続人の中に親権者とその子がいる時
特別代理人選任の申立をします。特別代理人との間に遺産分割協議をします。
未成年者に対し親権を行う者がいない時
未成年後見人選任の申立をします。未成年後見人との間で遺産分割協議をします。未成年後見人は一か月以内に財産目録を作成します。未成年後見には報酬を得ることができます。
相続人に判断能力がない人がいる時
相続人の中に精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者がいて遺産分割協議ができないときは家庭裁判所に成年後見開始の申立をします。選任された成年後見人と遺産分割協議をします。遺産分割協議につき急を要し成年後見人選任を待てない場合は成年後見開始の申し立てと同時に又はその後に財産管理者の選任申立てをすることができます。
相続人に任意後見契約を締結している人がいるとき
任意後見契約の有無及びその内容を確認します。その際には任意後見契約書に添付されている代理権目録で任意後見人の代理権の範囲に遺産分割が含まれているか否かを確認します。また法務局で登記事項証明書の交付を受けて代理権の範囲等を調べることもできます。任意後見契約の存在が確認できた場合、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行います。任意後見監督人が選任されれば任意後見契約の効力が発生し任意後見人が本人の代理人として遺産分割の手続きに関与することになります。ただし任意後見人自身が相続人の一人である場合には利益相反行為になりますので、任意後見人ではなく任意後見監督人が本人を代理します。
相続人中に後見人と被後見人がいる時
特別代理人選任の申立をします。
相続人中に保佐人と被保佐人がいる時
臨時保佐人選任の申立をします。臨時保佐人又は保佐監督人との間で遺産分割協議をします。
相続人の一人が海外在住である時
海外居住者と遺産分割協議書を作成する場合は印鑑登録証明書の代わりにサイン証明書を添付することになります。海外居住者と遺産分割協議が整わない場合は東京家庭裁判所に調停を申し立てます。
相次いで相続が発生した時
まず父の遺産につき母の相続分をどうするかも含めて分割協議をして母の取得財産を確定し、次に母の取得財産と固有財産につき分割協議をします。
相続分を指定する遺言があった時
遺言で相続文の指定がなされた場合はこれを具体化するために遺産分割協議が必要となります。遺産分割協議が整わない場合は遺産分割調停を申し立てます。
遺産からの家賃収入を分けてもらえない時
遺産から生じた家賃収入は遺産そのものではありませんが共同相続人全員の合意で遺産分割の対象に加えて協議することはできます。協議ができない場合は相続開始後から遺産分割がされるまでの間の家賃収入は法定相続部に応じて各相続人が確定的に取得することになりますので保管者がそれを渡さない場合は裁判にて請求します。
葬式費用を遺産分割で協議する時
葬儀費用の負担を含めた遺産分割協議ができたときはその旨を盛り込んだ分割協議書を作成します。相続人間で合意が出来ない時には民事訴訟で解決することになります。
調停審判による分割
遺産分割を禁止する事象が解消した時
遺産分割禁止の審判の取消しの審判の申立をします。
遺産の分割前に財産を管理する必要がある時
財産管理者を選任する審判前の保全処分の申立をします。
審判前の保全処分を取り消して欲しい時
審判前の保全処分の取消しの申立てをします原状回復の申立をします。
遺産の競売による換価審判を受けた後に代償金を支払えるようになった時
事情の変更があるとして競売を命ずる審判の取り消しを申し立てます。競売を命ずる審判の取り消しを受けて代償金を支払う内容の調停を成立させるかまたは遺産分割の審判を受けます。
遺産分割調停中に申立人が死亡した時
申立人死亡者の相続人が家庭裁判所に受継の申立をします。
遺産分割の審判に不服があるとき
遺産分割審判に不服がある相続人は審判をした家庭裁判所に即時抗告の申立をします。
遺産分割後の紛争等
遺産の一部を分割するとき
遺産の一部分割協議書を作成します。
遺産分割により共有取得した不動産を分割したとき
共有物分割の家事調停あるいは民事調停を申し立てます。
調停成立前には調停条項案を作成します。
調停が不成立の場合は、共有物分割の民事訴訟を提起します。
遺産分割後に認知された相続人が遺産を取得しようとするとき
遺産分割後に認知された場合、被認知者は価額の支払請求の調停申立をします。調停成立の見込みがたったら、他の共同相続人から現実に価額支払がされた事実又は他の共同相続人の価額支払の義務を記載した調停条項案を提示します。
調停が成立しなかった場合、訴訟提起します。
共同相続人の一部を除外して遺産分割協議を行ったとき
一部の共同相続人を除外して行った遺産分割協議は無効となりますので、新たに分割協議書を作成する必要があります。
新たな遺産分割協議がまとまらなかった場合は、一部の共同相続人を除外して行った遺産分割協議が無効であることの確認訴訟を提起します。
遺産分割協議で定めた代償金が支払われないとき
遺産分割協議で定められた代償金が支払われない場合、遺産分割後の紛争調整調停を申し立てます。調停が成立した後、相手方が代償金を支払わなかった場合には、強制執行、履行勧告、履行命令の申立などの手段があります。
調停が成立しなかった場合、訴訟提起します。
負担付遺贈を受けた者が負担した義務を履行しないとき
受遺者に対し、相当期間を定めて負担した義務の履行の勧告をします。
相当の期間内に履行がない場合、家裁に負担付遺贈に係る遺言の取消しの審判を申し立てます。
遺産分割協議に対する詐害行為取消権
遺産分割協議も詐害行為に該当しうるため、長男と三男を被告として訴訟上で詐害行為取消権を行使し、友人への法定持分に従った持分移転登記手続または長男と三男への持分移転登記の抹消登記手続きを求めていくことになります
遺産分割後に特定の財産が遺産でなかったことが判明した時
遺産分割全部の無効を主張し、その協議のやり直しを求めることができる場合もありますが、本件の例を含む多くのケースでは他の相続人全員を相手として他人の所有であったことによる瑕疵担保責任の履行を求め、話し合いがつけば相続人全員で合意書を作成します。
特別受益・寄与分・遺留分
特別受益
遺産分割の際に特別受益者がいるとき
弟と母が相続を主張しないのであれば相続分の無いことの証明書を作成して登記手続きをすることが考えられるでしょう。
寄与分
寄与分を定める合意が成立した場合
寄与分に関する遺産分割協議書の作成をします。
寄与分についての共同相続人間の協議がととのわないとき
相続人全員での話し合いがつかない場合は、遺産分割の調停の申立にあわせて寄与分を定める調停申立をします。
遺留分
遺留分を放棄したいとき
相続開始前であれば、遺留分放棄許可の審判を受ける必要があります。
相続開始後であれば、遺留分放棄書を遺留分を侵害する遺贈や贈与等を受けた者宛に送付します。
事前の遺留分放棄の許可を受けたものが、被相続人より先に死亡した場合は、代襲相続人は被代襲者が生存していたら名取得したはずである以上の権利を取得することは無いので、被代襲者の遺留分放棄の効果は代襲者にも及び、減殺請求はできません。
遺留分減殺請求をしたいとき
被相続人の死亡後、内容証明郵便や訴訟提起などの意思表示の到達、その年月日が確定できる方法で通知します。
遺留分算定の基礎となる財産の中に条件付き・存続期間の不確定な権利・義務がある時
当事者、この場合は、遺贈を受けた者が申立人となり、民法1029条2項に基づき、家庭裁判所に鑑定人の選任の審判を求めることになります。
遺産が1個の建物と敷地のみある場合に遺留分を主張されたとき
遺留分請求が期間内に行使されたものか調査し、時効期間が経過していれば消滅時効を援用します。
遺留分減殺請求者に対する遺贈若しくは過去の贈与を算定し、その遺留分を侵害しているか否かを検討し、遺留分に満ちていることを主張する。
生命保険金
被保険者である被相続人が死亡した時
死亡保険金請求書に必要事項を記載し必要書類を添付して保険会社に死亡保険金の請求をします。尚請求用紙や添付書類は個別の契約に応じて異なりますので、契約している保険会社に確認してください。
遺言により生命保険金の受取人の変更がされている時
遺言書に基づき死亡保険金の受取人を変更する場合、遺言執行者または生命保険契約に関する権利の承継者等が保険会社に対し死亡保険金受取人の名義変更を請求します。なお請求様式や添付書類は個別の契約に応じて異なりますので、契約している保険会社に確認してください。上記の通り保険金受取人を変更した後死亡保険金請求書に必要事項を記載し必要書類を添付して保険会社に死亡保険金の支払いを請求します。なお請求用紙や添付書類は個別の契約に応じて異なりますので、契約している保険会社に確認してください。
保険金受取人の死亡により名義変更をする時
死亡保険金受取人が死亡した場合は死亡受取人の名義変更手続きをする必要があります。なお請求用紙や添付書類は個別の契約に応じて異なりますので契約している保険会社に確認してください。
死亡保険金の受取人が法定相続人となっている時
死亡保険金請求書に必要事項を記載し必要書類を添付して保険会社に死亡保険金の支払いを請求します。なお請求用紙や添付書類は個別の契約に応じて異なりますので契約している保険会社に確認してください。なお上記のように保険金受取人が複数の場合、相続人の中から代表者を選任し他の法定相続人全員の同意を得た代表者選任通知書を作成する場合があります。
勤務先から死亡退職金を受け取る時
法律条例又は勤務会社の規定等により受給権者の定めがある場合には受給権者が死亡退職金支払請求書を作成し必要書類を添付して勤務先に提出します。受給権者の定めがない場合、相続人が受給権者となります。なお請求用紙や添付書類は勤務先書く退職金共済によって異なりますので勤務先書く退職金共済に確認してください。
健康保険死亡した健康保険被保険者を埋葬した時
被保険者が死亡した場合その者に生計を維持され埋葬を行う者が埋葬料の請求をします。埋葬料の支給を受ける者がいない場合は実際に埋葬を行った者が埋葬費の請求をします。
健康保険被保険者が死亡した家族を埋葬した時
被扶養者が死亡した場合被保険者が家族埋葬料を請求します。
市町村の国民健康保険葬祭費を受給するとき
夫婦で長く飲食店を営んできましたが先日私の妻が病気で急死しました。私と妻は国民健康保険に加入しています。私に支給される給付がありましたら内容と手続きを教えてください。
国民健康保険の被保険者が死亡した場合、葬儀を行った者が葬祭費を請求します。75歳以上の者が死亡した場合は後期高齢者医療葬祭費を請求します。
公的年金
国民年金
国民年金被保険者が死亡した時
遺族基礎年金は国民年金加入中の夫が亡くなり子のある配偶者または子供が残された場合に支給されます。寡婦年金は国民年金も第1号被保険者として10年以上保険料を納付していた夫が何の年金ももらわず死亡した時に妻に支給されます。死亡一時金は第1号被保険者として国民年金保険料を36ヶ月以上納付し、老齢基礎年金または障害基礎年金をもらわずに死亡した場合に遺族に支給されます。
国民年金の年金受給者が死亡した時
年金の支給は2ヶ月に1回振り込まれますので死亡した月によって未支給分の老齢基礎年金を請求することになります。国民年金の遺族給付は子のある配偶者が子のみに支給されるため今回のケースでは遺族基礎年金は支給されません。なお老齢基礎年金受給者死亡に伴い年金受給権者死亡届の提出が必要です。
国民年金の老齢基礎年金や障害基礎年金をもらわずに死亡した時は死亡一時金が支給されます。
厚生年金
厚生年金の被保険者が死亡した時
厚生年金の被保険者期間中の傷病がもとで初診日から5年以内に死亡した時は遺族厚生年金を受けることができます。国民年金の遺族基礎年金の受給者は子のある配偶者または子のみですが、厚生年金でも配偶者は受給資格があります。この事例では遺族厚生年金を受けることができます。国民年金の遺族基礎年金の他に18歳未満の子が2人いますので、子に対する加算額が加わります。遺族年金を受給する配偶者が事実婚の場合も可能。
厚生年金の年金受給者が死亡した時
妻の年金が850万円以下であれば遺族厚生年金は受けられます。年金の支給は2ヶ月に1回振り込まれるため死亡した月によっては未支給分を請求することになります。国民年金の遺族給付は子のある配偶者又は子のみに支給されますが今回のケースでは遺族基礎年金は支給されませんが代わりに中高齢の寡婦加算が支給されます。
厚生年金の被保険者が死亡した当時胎児であった子が出生した時
生まれた子供に遺族基礎年金・遺族厚生年金の受給権が発生します。遺族基礎年金に生まれた子供の加算額が加わります。
遺族年金受給者が行方不明になった時
遺族基礎年金・遺族厚生年金を受けているものの、所在が1年以上明らかでないときは、年金を受ける権利のある他の者が申請することができます。
年金給付に対して納得がいかない時
年金事務所の決定に納得がいかない時は決定のあったことを知った日の翌日から起算して3月以内に文書又は口頭で地方厚生局に置かれた社会保険審査官に審査請求をします。審査請求の決定に対して納得がいかない時は、社会保険審査官の処分の決定があったことを知った日の翌日から起算して2月以内、または厚生労働大臣の処分の決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に厚生労働大臣の所轄下にある社会保険審査会に再審査請求をします。
年金記録の訂正による年金の増額分を支払ってもらいたい時
過去に支給漏れのあった期間があれば支給漏れのあった全期間さかのぼって支給されます。これを時効特例納付と言います。遡って支払われる年金がある場合には支給当時の年金が現在価値に相当するよう物価上昇相当分として支援加算金が支払われます。
労災保険労働者が業務上の事由によって死亡した時
遺族補償年金の請求を労働者が勤務していた事業所を管轄する労働基準監督署に対して行います。請求による遺族補償年金を受ける遺族に対し給付基礎年金の前に自分を限度として、前払一時金が支払われます。葬祭料の請求を労働者が勤務していた事業所を監督する労働基準監督署に対して行います。
労働者が通勤災害によって死亡した時
遺族年金等の請求を労働者が勤務していた事業所を管轄する労働基準監督署へ行います。葬祭給付の請求を労働者が勤務していた事業所を管轄する労働基準監督署へ行います。請求により遺族年金を受ける遺族に対し給付日額の一斉に自分を限度として前払一時金が支払われます。
労働者が第三者行為災害によって死亡した時
第三者行為災害届を事業場を管轄する労働基準監督署に提出します。遺族年金葬祭給付の請求を労働者が勤務していた事業所を管轄する労働基準監督署へ行います。
障害補償年金の受給者が死亡した時
障害補償年金受給者が死亡した場合、すでに支給された障害補償年金等の合計額が障害等級によって定められた一定額に満たないと、その遺族に障害補償年金差額一時金が差額として支給されます。該当する場合は労働者が勤務していた事業所を管轄する労働基準監督署に対し請求を行います。なお実務的には受給権者が死亡した場合まず遅滞なく年金等受給権者死亡届を労働基準監督署に提出をします。それを受けて労働基準監督署は障害補償年金の差額や未支給の有無を確認の上、遺族に通知します。実際に差額が発生した場合、障害補償年金差額一時金の請求をすることになります。
遺族補償年金の受給者が死亡し順位の受給資格者が年金給付を請求するとき
遺族補償年金を受給していた者が死亡し、その死亡した者の他に支給すべき、遺族補償年金の受給資格者がいるときは、その遺族によって年金給付を請求することができます。
遺族補償年金の受給権者が保険給付を請求する前に死亡した順位の受給資格者が保険給付を請求するとき
遺族補償年金を受給する権利がある者は保険給付の請求をしないまま死亡し、その死亡者いた者に支給すべき年金給付がある時は、受給権者が死亡したことにより新たに受給権者となるものが未支給分の年金給付を請求することができます。またこの請求にあわせて第一順位の遺族補償年金の手続き及び転給の請求を行います。
遺族補償年金の受給資格者がいない時
労働者の死亡の当時、遺族補償年金の受給資格者がいない場合には、遺族補償一時金がその遺族に支給されます。遺族補償一時金の受給権者には遺族特別支給金が支給され、さらに遺族特別一時金も支給されます。
遺族年金の受給資格者がいない時
遺族一時金等の請求を労働者が勤務していた事業所を管轄する労働基準監督署へ行います。葬祭給付の請求を労働者が勤務していた事業所を管轄する労働基準監督署に行います。
労災給付に対して納得がいかない時
労働者災害補償保険審査官に対して審査請求を行います。労働者災害補償保険審査官の決定に不服がある場合は労働保険審査会に対し再審査請求を行います。
雇用保険未支給の失業等給付を請求する時
失業等給付の支給を受けることができる人が死亡した場合で、まだ支給されていないものがあるときは、配偶者・子・父母・孫・祖父母または兄妹姉妹であって、死亡当時生計を同じくしていた者は未支給の失業等給付を請求することができます。
相続税の申告・納税
申告
遺産を相続した時の相続税申告
相続または遺贈により財産を取得した人は、被相続人の死亡の日に所有していた遺産と相続開始時3年以内の贈与や相続時精算課税の贈与財産から被相続人に係る債務・葬儀費用を差し引いた合計額から、資産に係る基礎控除を超える額がある場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人死亡時の住所地を所轄する税務署へ相続税の申告を提出しなければなりません。
相続税の申告期限までに遺産分割が終わらない時
遺産が未分割であっても、相続税の申告書は法定申告期限までに提出しなければなりません。遺産分割を①配偶者の税額軽減、②小規模宅地の特例、③特定計画山林の特例の適用を受ける場合には、その申告書に申告期限後3年以内の分割見込書を提出します。さらに申告期限後3年以内に遺産分割が行われない場合は、遺産が未分割であることについてやむを得ない事情がある旨の承認申請を行います。未分割で相続税額に過不足が生じた場合は更正の請求又は修正申告を行います。
遺産分割の協議があった時
当初の遺産分割に重大な瑕疵あるいは錯誤があり、遺産分割が無効である場合以外は、遺産分割協議のやり直しは相続人間の贈与と認定されますので、贈与税の申告が必要です。当初の遺産分割に無効原因があったため、遺産の再分割がなされた場合、相続税額が過大になった時は、更正の請求をすることができる。過少になった時は修正申告をすることになります。
遺留分減殺請求がされた時の相続税申告
遺留分権利者が遺留分減殺請求をして相続税の申告期限までに現物返還等が確定した場合には、遺留分権利者と受遺者等は、その減殺請求の確定により相続税の申告及び納付をしますが、返還すべき財産の価額が未確定の場合は減算請求がなかったものとして、相続税の課税価格を計算して申告をします。相続税の申告後に遺留分権利者が遺留分減殺請求に基づき財産を取得し、納税すべき税額が新たに生じたときは期限後申告をします。またその相続税額が当初申告より増加することとなった場合には、修正申告をします。一方、受遺者等は当初取得した財産が減少したことにより相続税額が課題となった場合には、更正の請求をして、相続税の還付を受けることができます。
相続税の申告をした後に相続人の人数に変更があったとき
相続税の申告書の提出後、相続人の人数に移動が生じたこと等によりその申告に係る課税価格及び相続税額が過大となった場合は更正の請求を行うことにより過納額の還付を受けることができます。
相続時精算課税と暦年贈与
相続時精算課税適用財産は相続により取得したものとみなして相続税の課税価額に加算されます。そしてその財産について贈与税を納付していた場合は、その金額を受贈者の相続税額から控除し、控除しきれなかった金額は相続税の申告書を提出することで還付が受けられます。暦年課税方式の場合は相続課税前相続開始前3年以内の贈与に限って相続税の課税価格に加算して相続税の計算を行います。そしてその受贈財産について贈与税を納付していた場合は、贈与税額控除の適用を受けられます。この場合、控除しきれない金額があっても還付されません。相続税の申告をする場合、他の相続人等が被相続人から受けた相続開始前3年以内の贈与または相続時精算課税制度適用の贈与に係る贈与税の課税価額の合計額については、税務署長に対し開示を請求することができます。
死亡した者が個人事業を営んできた時
所得税及び復興特別所得税の準確定申告書を相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に提出します。所得税について青色申告を行っている場合に純損失が生じた時は準確定申告による純損失の繰戻還付請求ができます。死亡したものが消費税の課税事業者の場合には、消費税の準確定申告書を上記と同様相続開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に提出します。被相続人の事業開始等の届出書を提出しなければなりません。被相続人の事業を承継した相続人は事業開始にあたり各種届出書を提出しなければなりません。
更正処分受けてから3ヶ月以内に再調査の請求をします。再調査の請求の結果においても不服の時は審査請求をします。それでも不服の時は訴訟します。
特別縁故者の相続税申告
特別縁故者が家庭裁判所の審判により相続財産の分与を受けた場合は、そのものが被相続人から相続財産遺贈により取得したものとみなされる。財産分与の財産の時価が遺産に係る基礎控除額を超えている場合等は相続税の申告が必要となります。
遺産を国又は公益法人等に寄付したい時
相続や遺贈によって取得した財産を相続税の申告書の提出期限までに国や地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄付した場合や特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、その寄付をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。
納税
納付の手続き
相続税の納付は申告期限と同じく相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に原則として金銭で納付しますなお相続税申告書は被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長へ提出しますが納税についてはその諸葛靚無証明を記載した納付書を持参して全国どこの金融機関等からでも老化することができます相続時精算課税適用者等について相続税を還付される場合には還付される税額の受け取り場所の附票を添付して税額の還付を受けます相続人が非居住者の場合には納税管理人の届出手続きが必要になります。
相続人が限定承認をした時
相続人等が限定承認をした場合、被相続人が相続財産を相続開始時の時間に相当する金額により譲渡したものとして所得税の準確定申告を行います。
未登記の不動産を相続した時
相続人が未登記家屋を相続した場合、本来はほとんど受けて相続登記を行うべきですが、固定資産税については納税義務者変更届出書を市区町村に提出し、名義変更手続きを行えば相続人の名義で固定資産税の納付書が送付されます。
相続登記が完了するまでの納税義務者の代表者を指定する時
不動産の相続登記が未了の間も、固定資産税が発生します。相続登記が完了するまでの間に相続人に仮固定資産税の納付又は還付に関する納税通知書を受領するために、相続人代表者指定届の提出しなければなりません。この届出書は固定資産税の納税に限定したもので法的に相続する資産の所有権を確定するものではありません。なおこの届出書を提出した後に相続登記を放った場合は登記を優先します。
納税猶予
農地を相続した時
相続税の納税猶予の特例の適用が受けられる農業相続人は被相続人の相続人で相続税の期限内申告書に納税猶予を受ける旨の事項を記載して提出しなければなりません。納税猶予期間内の手続きとして相続税納税猶予の継続届出書の提出が必要です。納税猶予の適用を受けた相続税額は一定の要件に該当する場合に免除されます。
山林を相続した時
相続税の納税猶予の特例の適用が受けられる林業経営相続人は相続税の期限内申告書に山林についての納税猶予の特例の適用を受ける旨の事項を記載して提出しなければなりません。納税猶予期間内の手続きとして山林についての相続税の納税猶予の継続届出書の提出が必要です。
取引相場のない株式等に関する遺留分の特例を受ける時
旧代表者の推定相続人及び後継者の全員で合意書面を作成します。後継者はその行為をした日から1ヶ月以内に経済産業大臣に対して合意についての確認の申請を行います。後継者はその確認を受けた日から1ヶ月以内に家庭裁判所に対して遺留文の算定に係る合意の許可の申立てを行います。後継者には親族ない後継者の他親族外後継者も含まれます
非常上場株式等についての相続税の納税猶予の特例を受けていたものが亡くなった時
後継者の死亡があった場合には非常上場株式等についての相続税の納税猶予の免除届出書を提出することによりその死亡があった時において納税が猶予されている相続税の全部又は一部についてその納付が免除されます。平成30年度の税制改正において措置された特例においても上記の一般措置と同様の手続きが必要とされています。
相続税の申告納付後に納税額が過大であることが判明したとき
既に行った申告の税額が課題であった場合に更正の請求が可能な期間内であるときは更正の請求を行うことになります。
その他
相続により取得した財産が災害によって被害を受けた時
相続または遺贈により取得した財産が災害によって被害を受けた場合において一定の要件に該当するときには相続税が軽減されます。法定申告期限前に災害があった場合は相続等により取得した財産の価額から被害を受けた部分で保険金損害賠償金等で補填されなかった部分の価額を控除して課税価格を計算することになります。法定申告期限後に災害があった場合には災害のあった日以後に納付すべき相続税額で課税価格の計算の基礎となった財産の価額のうち被害を受けた部分で保険金損害賠償金等で補填されなかった部分の価額に対応する金額が免除されることになります。
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例を受ける時
相続または遺贈により財産を取得した者がその財産を相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過するまでの間に譲渡した場合は、譲渡所得の金額の計算上相続税額のうち一定の金額が取得費に加算される特例を適用することができます
売買契約締結後売買代金受領前に相続が開始した時
譲渡所得の計上時期は原則として資産の引渡し日ですが、納税者の選択により資産の譲渡に関する契約効力発生日とすることもできます。従って売買契約中に売主が死亡した場合は資産の引渡し日を選択したときは相続人の譲渡所得として契約効力発生日を選択したときは被相続人の準確定申告で譲渡所得として申告します。
相続空き家を譲渡した場合の譲渡所得の特例を受ける時
相続または遺贈により被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を取得したもので相続開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にその取得した被相続人居住用家屋等を一定の要件のもとに譲渡した場合には、その譲渡した日の属する年の翌年3月15日までに確定申告書を提出して被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例を受けることができます。
馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
〒604-0024
京都市中京区下妙覚寺町200衣棚御池ビル2階
TEL:075-254-8277 FAX:075-254-8278
URL:https://www.bababen.work