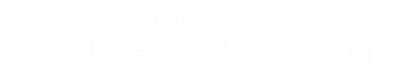労働保険に関してよくある質問

労災発生時に使用者が労災保険に未加入のケース
労働者を1人でも使用する事業主は、個人経営の農業、水産業で労働者数5人未満の場合、及び個人経営の林業で労働者を常時には使用しない場合を除き、強制適用事業として労災保険制度の適用を受け、加入の手続をとり、保険料を納付しなければなりません。
保険料は、全額、事業主負担です。
労災保険の適用事業の事業主につきましては、その事業が開始された日に、その事業について労災保険の保険関係が成立します。
労災事故の際に使用者が労災保険に加入していなかったとしても、事業を開始した時点から強制適用事業所として国との間に労災保険関係が成立しており、労働者は労災保険の受給申請手続をすることが可能です。
もっともこの場合、使用者が労災保険に加入しなかったことが重大な過失である場合、労働者に支給された労災給付金の40%を、故意である場合には、100%のお金を国に納付しなければいけません。
休憩時間中の災害は労災保険が使えるか
労働者は休憩時間を原則として自由に利用することができますが、事業場施設内で行動している限り、事業主の支配下にありますので、業務遂行性があります。
しかし、その間の行為は私的行為ですので、休憩時間中の災害が、事業場施設、又は、その管理に起因することが原因で発生したことを立証されなければ、業務起因性はありません。
但し、飲水、用便など生理的要求による行為や作業と関連する必要行為、合理的行為は業務に付随する行為だとされています。
例えば、休憩中の喫煙は微妙な問題を含んでいますが、休憩中に喫煙しようとして、ガソリンの染みた作業衣に引火して火傷をした場合、労災認定がされていますので、転倒事故が事業場内で発生していることから、喫煙を生理的要求によるものに準じた行為とすれば、労災認定されることがあります。
出張中の災害は労災保険が使えるか
出張中につきましては、その用務の成否や遂行方法などについて、包括的に事業主が責任を負っているので、出張過程の全般について、事業主の支配下にあり、単純な私用行為とみなされない場合は業務遂行性が認められます。
職場の同僚との喧嘩は労災保険が使えるか
労働者は、人間同士で組織となって業務を行っていますので、その中で仕事のことに関して一方的に暴力を受けたりした場合、災害としての負傷の原因が業務にあって、業務と負傷との間に因果関係があれば、その負傷は業務起因性が認められて業務災害となります。
しかし、業務に起因しての暴行にみえても、普段の私的関係による単なる喧嘩とみられる場合は、業務起因性が否定され労災と認定されないこともあります。
会社でのイベント中の災害は労災保険が使えるか
スポーツ大会や慰安旅行など、会社行事に参加している最中の災害について、労働基準監督署は、主催者、目的、内容、参加方法、運営方法、費用分担等を総合的に考慮して労災と認定するか否かを判断しています。
一般的には、業務命令があったり、事実上の参加強制がないと業務遂行性は認められず、労災と認定されない傾向にあります。
残業時間が多く、帰宅時間も深夜になることが多く、体調も悪くうつ状態になり、自殺(自死)してしまいました。会社に責任を問うことは可能でしょうか。
仕事によるストレスが原因で精神障害を発症したり、自殺(自死)をする労働者が増加しています。
労働基準監督署は、精神障害によって、正常な認識、行為選択能力が著しく阻害されたり、自殺(自死)を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態と認められる場合には、いわゆる過労自殺(自死)として業務起因性を認め、労災認定をしています。
この過労自殺(自死)が長時間労働を放置し、労働者の職場環境の改善をしないことにより発生したことが立証されれば、あなたは、会社に対し安全配慮義務違反や、不法行為を主張して損害賠償請求することが可能です。
会社の労災隠しに対する罰則はあるか
事業者は、労働者が労災により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく労働者死傷病報告書を労働基準監督署長に提出しなければならないことになっています。
これに違反して報告をしないとか、虚偽の報告をすると、50万円以上の罰金に処せられることになります。
労災隠しの背景には、事業者の無事故記録のノルマがあって、現場管理者が責任を問われるのを恐れるとか、労災事故で官公庁の工事の入札に参加できなくなる等の事情があります。
また、労災件数が少ないと労災保険料が安くなるなどのメリット制の影響もあると思います。
労災隠しは犯罪ですので、被災労働者は事業者に屈することなく、労働基準監督署に労災保険受給の申請をすべきです。
この際、事業主の証明などはいりませんから、自分だけの行為で申請ができます。
後遺障害の等級認定にあたって、自賠責保険で認定を受けるべきか、労災保険で認定を受けるべきか
自賠責の後遺障害等級は労災の等級をまねて作られていますので、後遺障害の内容は同じです。
労災での認定の場合は、労働基準監督署の顧問医が、被災労働者と直接面談し、後遺障害の有無とその程度を認定していますので、比較的、公正な判断がされることになります。
これに対し、自賠責での認定の場合は、自賠責損害調査事務所が、被災労働者と直接面談することなく、診断書等の書類審査のみで後遺障害の認定をしますので、被災労働者の症状に合致した判断がなされることは少ないといっても過言ではありません。
しかも、自賠責損害調査事務所が損害保険会社の利益に沿った調査をしているのではないかとの疑いもあります。
業務上や出退勤時における交通事故の労災の場合は、自賠責ではなく労災に対し、障害補償給付(後遺障害)の申請手続をすることが良いケースが多いです。
下請会社の労働者が、元請会社の職場内で、元請会社の社員の指揮、監督を受け、元請会社の機械を使って部品製造の仕事をしていますが、労災事故にあってしまったケース
労働者と直接雇用関係にある会社や個人事業主は、安全配慮義務違反が認められる場合、損害賠償の支払義務を負います。
直接雇用関係にある会社や個人事業主ばかりでなく、元請企業がある場合、元請企業が損害賠償責任を負うこともあります。
最高裁判所は、「下請企業の労働者が元請企業の作業場で労務の提供をするにあたり、元請企業の管理する設備、工具等を用い、事実上、元請企業の指揮、監督を受けて稼働し、その作業内容も元請企業の従業員とほとんど同じであった場合には、元請企業は、信義則上、その労働者に対し安全配慮義務を負う。」と判示しています。
したがいまして、あなたが下請会社に雇用される労働者であり、下請会社に対しては勿論のこと、元請会社に対し損害賠償請求することも可能です。
下請会社に資力がない場合には、下請会社から損害賠償を得て被害回復することができます。
派遣先での労災事故について
派遣労働者は、労働者派遣法により禁止された違法派遣であると否とを問わず、派遣会社に雇用された上で派遣先会社に派遣され、直接の雇用関係のない派遣先会社の指揮監督命令下で業務に従事することになります。
派遣先会社はあまり派遣労働者の安全に配慮しない傾向にあり、派遣労働者が派遣先で労災事故にあうこともあります。
派遣先の間では直接の雇用関係はありませんが、派遣先の指揮監督下で仕事をし、プレス機械の不備で指を切断したのですから、派遣先に対して、安全配慮義務違反を理由として損害賠償請求することが可能です。
又、派遣元の責任ですが、あなたが、派遣先で就業することについて、労働者派遣法31条は、派遣元に対し適切な配慮を求めていますので、場合によったら派遣元もあなたに対し安全配慮義務を負う場合もあります。
この場合、派遣先ばかりでなく、派遣元に対しても損害賠償請求することが可能です。
労災給付の時効について
療養補償、休業補償、葬祭料は、労災事故が発生してから2年以上経過しますと時効が完成し、それ以前の分は請求できなくなります。
障害補償給付(後遺障害)と遺族補償は5年以内に請求しないと時効が完成し、請求できなくなります。
馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
〒604-0024
京都市中京区下妙覚寺町200衣棚御池ビル3階
TEL:075-254-8277 FAX:075-254-8278
URL:https://www.bababen.work