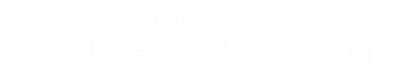介護事故に関する証拠
介護事故において、その事故が生じることがその時点において予見できたかどうか(「予見可能性」といいます)を立証する必要があります。
そのためには、下記証拠を集める必要があります。
介護サービス契約書・重要事項説明書
平成12年4月介護保険制度開始により、介護サービスの利用が、従来の「措置」から「契約」へ移行しました。適切な介護保険サービスの利用や提供がなされるよう、「契約書」及び「重要事項説明書」の作成が求められます。
そして、介護事故についても契約が定めた施設側の義務違反があるかどうかで責任の有無が決まることになります。
介護保険被保険者証
65歳以上の人を対象に、住んでいる市町村から自動的に交付されます。介護保険のサービスを受けるときに必要となります。介護保険被保険者証に有効期限はありませんが、介護認定には期限があります。
要介護状態の区分、居宅介護支援事業者または介護予防支援事業者及びその事業所の名称、介護保険施設等が記載されています。
要介護認定票
要介護認定とは、介護保険サービスの利用希望者に対して、どのような介護がどの程度必要かを判定するためのものであるので、介護事故が発生したときに求められた介護をされていたかの判断の基準となります。
介護保険主治医意見書
介護保険法では、被保険者から要介護認定の申請を受けた市町村は、当該被保険者の「身体上または精神上の障害(生活機能低下)の原因である疾病又は負傷の状況等」について、申請者に主治医がある場合には、主治医から意見を求めることとされています。
個別援助計画書(通所介護計画書)(サービス計画書)
デイサービスの生活相談員が中心となって作成する書類で、ご利用者やその家族がデイサービスに求める希望・要望が書かれたケアプラン(居宅サービス計画書)に基づき作成します。ケアプランとは、被介護者本人とその家族がより充実した生活を送れるように長期的・短期的な目標が設定されています。ケアマネジャー(介護支援専門員)が作成します。ケアプランは「居宅サービス計画」「施設サービス計画」「介護予防サービス計画」の三種類があり、要介護度・要支援度によって利用できるケアプランも異なります。
介護事故では、計画書に記載されていた介護内容がなされていないために生じたということになれば、過失があったということになるでしょう。
フェースシート
医療・福祉分野で援助を目的とした情報収集において使用される利用者の「氏名」「年齢」「性別」「家族構成」「健康状態」などの基本データをまとめた用紙。
モニタリング票
援助計画の実施の状況等の報告書です。
業務日誌・介護記録・介護日誌
何時何分にどのような介護がなされたか、その内容が記録されており、介護事故が生じた原因を分析する資料となります。
通院先の医師や施設嘱託医の作成したカルテ、レントゲン、処方箋の記録など
介護事故が発生した後、どのような傷害を負ったのか、後遺障害が残ったのか、死因は何かなどの分析のための資料となります。
施設構造図、建物の図面、ヒヤリハットシート、人員配置票・シフト表
主に介護事故が発生しないようにするための措置(回避措置)を取るための手立てをとっていたかどうかの判断のための資料となります。
これらの証拠を隠匿等されないように、裁判所を通じて証拠保全をすることも検討すべきでしょう。
馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
〒604-0024
京都市中京区下妙覚寺町200衣棚御池ビル2階
TEL:075-254-8277 FAX:075-254-8278
URL:https://www.bababen.work