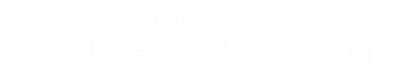絶対的必要記載事項について
労働時間に関する事項(89条1号)
「始業及び終業の時刻」については、具体的な時刻を定める必要がある。
同一事業所で労働者ごとに始業・終業時刻が異なる場合、区分ごとに定めが必要である。
始業・終業時刻を画一的に定めないこととする一定の者については、委任規定を設けて個別契約で定めることができる。「始業・終業時刻及び休憩時間については、個別契約によるところとする。」
監督又は管理の地位にある者等の労基法41条で労働時間等について労基法の適用除外とされている者についても就業規則の作成義務はあります。当該就業規則の始業・終業時刻等必要記載事項についての規定を適用除外とすることはできません。
休憩時間の繰り上げ・繰り下げ変更が行われる場合は、変更権について規定を置くことが必要である。
「休日」(労基法89条1号)については、その日数、与え方等を記載する必要がある。
法定休日を特定しないのが労務管理上適切である。所定休日を含む休日のうちどの日が法定休日かを特定してしまうと、その法定休日に就労した場合、当然に3割5分増の割増賃金が発生することになる。
休日振替については、就業規則上振替権についての定めが必要であるが、他方、代休については、代休付与自体には就業規則上の根拠規定は不要であるが、賃金控除のためには根拠規定が必要である。
「休暇」については、労基法上付与が義務付けられている年次有給休暇、産前・産後の休暇及び生理休暇のみならず、育児・介護休業法により義務付けられている育児休業や介護休業、看護休暇等を記載する必要がある。
賃金に関する事項(2号)
昇給に関する事項のみならず、降給についても規定すること。
退職に関する事項(3号)
当然退職事由・合意退職・辞職・解雇、有期契約の場合であれば期間満了による終了等、全ての事由を記載する必要がある。
昇給の定め方については、定め方いかんにより、労働者が取得する権利となりうるので、慎重に検討すること
相対的必要記載事項について
制度として実施する場合には記載しなければならないのが「相対的必要記載事項」です。
以下注意点をみていきましょう。
「退職手当」については、支給条件が明確であり、その請求権が退職を要件として在職中の労働全体に対する対価として具体化する権利であれば、退職一時金・退職年金も該当する。
退職手当・臨時の賃金等・賞与については、昇給でも前述した通り、定め方いかんにより、労働者が取得する権利となりうるので、慎重に規定すること
労働者に食費や作業用品、社宅費、共済組合費等の経済的負担を課する場合、労基法89条5号により、これらの負担額、負担方法等を定める。
「安全及び衛生」(6号)について、労安衛法との関連に注意する。例えば、労安衛法66条1項の健康診断の実施は使用者の履行義務ですが、同法66条の5の健康診断実施後の措置は啓発規定にすぎないので、これを就業規則により義務化するべきか否かは慎重にするべき。
任意記載事項について
必要記載事項に含まれない業務命令権についても、就業規則に記載することにより初めて取得可能となる業務命令権についてはあらかじめ記載しておく必要があります。
就業規則に記載しなくても取得できる業務指示権についても、あらかじめ記載しておくことが適切でしょう。
馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
〒604-0024
京都市中京区下妙覚寺町200衣棚御池ビル2階
TEL:075-254-8277 FAX:075-254-8278
URL:https://www.bababen.work