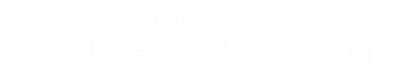不動産の明渡しの強制執行の流れはどのようなものですか?

裁判所の執行官室に申し立てて、下記のとおり、手続が進みます。
①不動産明渡の執行申立
債務名義正本の送達証明申請をし、送達証明書を入手します。
執行費用は債務者の負担になりますが、執行予納金を予め納付する必要があります。
執行官が申立書や必要書類の受付と審査をし、受理されれば、執行予納金の保管金提出書が交付されます。執行官との面接票が交付されるケースもあります。
②執行日時の指定等
執行官との事前打ち合わせで、明渡催告の日時が指定され、申立人側は、明渡業者・運送業者・解錠技術者の手配をします。これらの費用は予納金とは別途必要となりますので注意です。
③明渡催告期日
相手方に対し、強制執行実施予定日(断行期日)を催告し、引渡期限(催告日から1か月後、なお断行期日はこの数日前が多い。)、占有移転が禁止されることを記載した公示書が貼り付けられます。
また、明渡作業及び目的外動産の保管費用の見積もり作業が行われます。
相手方が不在の場合が多く、あらかじめ住民票を取り寄せて所在を示しておけば、占有が認定され、解錠されます。
なお、未払い賃料に基づく動産執行をあわせて申し立てているときは、動産差押を行います。
④任意交渉・引渡期限の延長等
断行期日までに和解成立により明渡が完了すれば取下書を提出します。
⑤断行期日
申立人・またはその代理人が必ず立会いします(民事執行法168③)。
目的外動産は、搬出後、債務者・その代理人・同居の親族・使用人に引渡しますが、引渡ができない場合は、執行官により即日売却されます。
ただし、相手方が引き取りを希望する場合、大量の家財道具等が残置されている場合、高価な物が残置されている場合は、即日売却はできず、一カ月間ほど保管替えされます。
保管費用は本来相手方負担ですが、お金がないことも多く、実際は申立人が負担となるケースがほとんどで、執行予納金とは別に実費として想定する必要があります。
⑥引き渡しを受ける
申立人側は、再び占有されないように、すぐに鍵の交換をする必要があります。
馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
〒604-0024
京都市中京区下妙覚寺町200衣棚御池ビル3階
TEL:075-254-8277 FAX:075-254-8278
URL:https://www.bababen.work