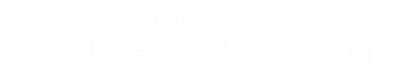家賃増額請求をした場合の算定方法を教えてください
貸主側の事情から賃貸建物を建て替える場合における新しい建物の賃料を算定した東京地判昭和58年8月25日判時1110.98は、旧建物から新建物への建て替えが改装するよりも新築の方が経済的であるという家主側の事情に基づくところを考慮して従前賃料の136パーセントが相当賃料であると判示しました。
利回り方式(積算法)
①建物所有者が敷地所有者であるか、借地権者であるかは借家関係とは別個の法律関係です。
②社会経済上、建物の存立及び利用は敷地を離れて存在せず、建物の経済価値は建物それ自体の物権的価値のほかに当然に敷地利用価値を含みます。
投下資本額
東京高判昭和46.9.10判タ271.323は建物価格と土地利用価格(地価の70%)の合計額の50%を借家権価格とみてその残額をもって借家のための投下資本額としました。
この考え方は土地価格のうちほぼ三等分したものを土地所有者、建物所有者並びに建物利用者(借主)にそれぞれ配分した上で、建物所有者が投下した資本額は土地価格のほぼ3分の1と建物価格の2分の1との合計額であるとしました。
また、東京地判昭和51.8.17判示850.52は、借地上の借家のケースにつき、建物価格の30%と借地権価格の30%の合計額が借家権価格であるとし、投下資本額は建物価格の70%と借地権価格の70%の合計額であると判示しました。
借家権価格の成熟した地域では、およその標準として土地については借地権の20~40%前後(土地建物が同一所有者の場合は借地権を想定します。)、建物については建物価格の30%~50%前後といわれています(一戸建借家について。アパート、マンションは除く。)。
期待利回り
東京高判昭和46.9.10は借家権価格を控除した土地建物価格に期待利回り年8%を乗じました。
東京地判昭和51.8.17は建物の期待利回り年10%、土地の期待利回り年8%としています。
算定方式
建物価格×借家権割合(1-0.3)×建物の期待利回り0.10=A(純賃料の一部)
借地権価格×借家権割合(1-0.3)×土地の期待利回り0.08=B
※借地権価格=更地価格×0.7(借地権割合)
建付地としての価格×借地権割合0.7×借家権割合(1-0.3)×土地の期待利回り0.08=B´
※建付地とは自住自用地であるが、借家しているとき、「自住」とはいえない。
(A+B+必要諸経費等(建物の償却費))÷12(月)=借地上の借家の積算家賃月額
(A+B’+必要諸経費等(建物の償却費))÷12(月)=所有地上の借家の積算家賃月額
→こうして求められた積算家賃は継続家賃ではないので、改めて当事者間の契約締結の経緯、賃料改訂経過、期間など諸般の個別的事情による修正が必要です。
スライド方式(騰貴率比例法)
従前家賃額に土地建物価格の上昇率あるいは消費者物価指数などの騰貴率を乗じて相当家賃を求めます。
従前賃料
賃料決定の客観的要素及び主観的事情が一応正当に反映されている場合は基礎とすることができます。
家賃は借家の対価ですが、建物利用の対価部分と敷地利用の対価部分に分析でき、純家賃と地代相当分と呼ぶこともあります。
騰貴率
一つの騰貴率を乗ずる裁判例と純家賃額と地代相当分に各対応した騰貴率を乗ずる裁判例があります。
騰貴率を土地建物価格の騰貴率によって依拠する立場と消費者物価指数の騰貴率による立場とに分かれています。
比較方式(賃貸事例比較法)
地代のケースと同様です。
総合方式と差額配分法
地代のケースと同様です。
馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
〒604-0024
京都市中京区下妙覚寺町200衣棚御池ビル3階
TEL:075-254-8277 FAX:075-254-8278
URL:https://www.bababen.work